連合艦隊司令長官を務め、多くの作戦の指揮を執った山本五十六。
彼は、幼い頃から負けず嫌いで、戦争の時代に生まれた宿命ゆえに、軍に所属することとなります。
信念を持ち、人としても軍人としても優秀であったため、様々な逸話を残し、数々の武勲をあげたため、今でも彼のファンは多いです。
山本五十六の残した名言を深く掘り下げ、どのような意味があるのか見ていきましょう!
山本五十六のビジネス・教育・子育てに共通する育成論の名言

話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。

筆者は、この名言を、子育てと仕事の場において大切にしたいと思います。
まず子育てでは、子どもを認め、信じること。簡単なようで難しく、答えのない問題に日々、これでよかったのかなと思いつつも、考え続け探し続けることが大事だと思い、この名言を心において子どもたちと向き合っていきたいです。
次に仕事では、中堅の立場となり、仕事内容を新人さんに教える機会も増えました。
共に仕事をする同僚に感謝し、声に耳を傾け、自分自身も成長し続けたいです。
子育てに関しては、ドロシー・ロー・ノルトさんの詩で世界中に知られる『子は親の鏡』という詩も、幼少期の『人材育成』に関して鋭い視点で、私たちに向き合うべき事柄を教えてくれています。
認め、励まし、信じるまなざしで子と関わることで、子どもの心や人格形成に大きく影響することが伝えられています。
ドロシー・ロー・ノルトさんの詩に関する記事はこちらです。
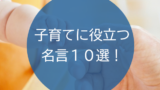
なぜなら、われわれ実年者が若かった時に同じことを言われたはずだ。
人は、世代によって価値観や考え方が異なります。

子育てに対する考え方なんかも、現在と親世代とでは考え方が大きく異なります。
世代だけでなく、他人の持つ考え方や文化など、自分と異なる部分を尊重し、理解する姿勢は今後も持ち続けたいと感じました!
山本五十六が最前線で生きた時代は、男性が社会的に優位な風潮がありました。
天下を動かすような、どんなに優れた男性でも、自分の妻には頭が上がらないことを、この名言では言っています。
この名言からはは、その人の才能を見極めて肩書を与えるか、人をよく見ることの必要性が伺えます。
才能の定義は、「物事をうまくなしとげるすぐれた能力。技術・学問・芸能などについての素質や能力」です。
生まれ持った素質はあるかもしれませんが、才能は、生まれ持ったものではなく、その人の努力や経験の中で得たスキルや能力も大きく関係します。
この名言によると、中位の才能を持つ者に肩書を与えると、今まで見えていなかった才能を開花させる良いきっかけになり、大きな才能を持つ者には肩書は足かせになってしまうんですね。
さらに、才能が乏しい者に肩書を与えると肩書の方が汚れてしまうと、この名言では言われています。
山本五十六の連合艦隊司令長官として組織を良くするために「誰にどの役職を与えるか」といった人を見る眼が伺える名言ですね。
小才は、縁に出合って縁に気づかず
中才は、縁に気づいて縁を生かさず
大才は、袖すり合った縁をも生かす
柳生宗矩(剣術家)
これは、人のご縁の大切さや、いただいたご縁をどう活かすかを表した名言です。
才能と人間性は相関していることが伺えます。
何かを極めようとすれば、それに伴って心の在り方や自分自身の内側を省みながら精進することは必須になってきますしね。
それを克服しようとして進歩するものなのだ。
負い目とは、自分が他人に対して恩義や迷惑をかけてしまったと感じる心情を意味します。
しかし、そういった後悔が、自分が進歩・成長するためのエネルギーとなるのです。
人の上に立つ者でも、完璧な人間なんていません。
自分が持つ「負い目」と向き合うのは、苦しい時もありますが、克服するには、まず自分の不十分な点を認識することからです。

誰もが抱える人間の弱さを肯定し、認めたうえで、優しいまなざしで見守るような、深い愛情がこの名言には溢れていますね。
職分を如何に巧みに処理するかによって、その人の値打ちがきまる。
社会で生きている以上、多くの人が何らかの仕事に就いています。
そんな仕事に向き合う中で、楽しいこと、やりがいがあることもあれば、大変なこと、辛いこともあるでしょう。
人にはそれぞれ得手・不得手、向き・不向きがあるものです。
上司は部下の個性を見極めて能力を引き出すという役割があります。
また、部下は上から与えられた仕事に責任を持って取り組む必要があります。
会社は組織であり、それぞれが異なる役割を持って、密接に関係しあい、好循環を生み出していけるかが、組織が効果的に機能できる要になります。
その組織をつくっているのは、他でもない私たち一人一人であり、人としての真価が問われることになるのです。
問題が発生し、苦しい場面に直面したとしても、創意工夫を怠ることなく、自分自身を高めようとする意識があれば、どんな問題もチームで乗り越えてゆけるでしょう。
ちなみに、「巧みに処理」とは、「要領よくこなす」という意味ではないそうです。
「自分の仕事に誠実に取り組み、きちんとなし遂げること」を指しているそうですよ。
1.「事実や真実と違うこと」という意味で、正しくないことを言います。
2.「あやまちを犯すこと」という意味で、うっかりしくじることを言います。
3.「事故や予想外の出来事」という意味で、良くない災難が起きることを言います。

誤りが起きても真摯に誠実に対応することで、その人の人間性が垣間見えますね。
山本五十六の男の修行・我慢に関する名言

云い度いこともあるだろう。
不満なこともあるだろう。
腹の立つこともあるだろう。
泣き度いこともあるだろう。
これらをじつとこらえてゆくのが男の修行である。
この名言も山本五十六の有名な言葉です。
現在となっては、古き良き言葉といった位置づけになるのではないでしょうか。
世の中は理不尽なことや辛いことがたくさんあります。
しかし、どんなに辛いことや理不尽なことがあっても、簡単には「逃げ出さず」「愚痴をこぼさず」「弱音を吐かない」といった意味が、この名言では表れています。
修行というのは、自分自身との戦いであり、我慢強く耐えることでもあります。
そうした我慢をしながらやるべきことはきちんと行い、切磋琢磨することで自分の内側を磨いていく、それが「男の修行」であると山本五十六は伝えています。

私は父に対して尊敬していることがあり、それは仕事に対して「弱音」や「愚痴」を決して言わないことです。
父と私はもともと同業者であったので、仕事内容に対する大変な部分はよくわかります。
しかし、父は常々「働かさせてもらっている奉公だ」と言って、誠実に仕事に向き合っていました。
父は見た目は決して強くなく、華奢な方です。
しかし、芯の強さや優しさといった面では遥かに優れたものを持っていると感じました。
その反面筆者は、まだまだ未熟で、愚痴や弱音を吐かないとやっていられないタイプです…。
修業とは程遠いですが(笑)
さいごに
いかがでしたでしょうか。
山本五十六さんの名言からは、深い人間理解と、人を信頼し待つことの大切さが伝わってきましたね。

子育てや仕事で困難な壁に当たったときは、この名言を思い出したいと思いました。
当サイトでは他にも、経営者として人材育成を大切にしていた松下幸之助の名言を詳しく紹介していますのでご覧ください。
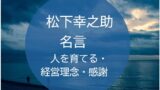
最後まで読んでいただきありがとうございます。
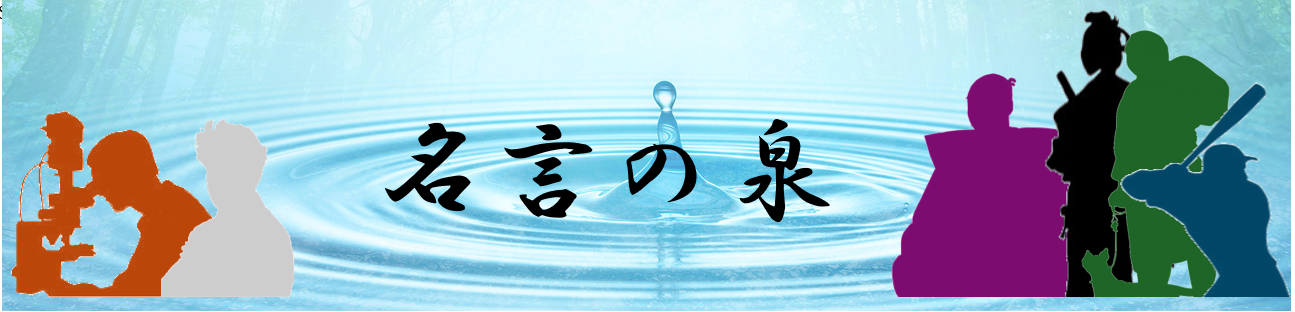
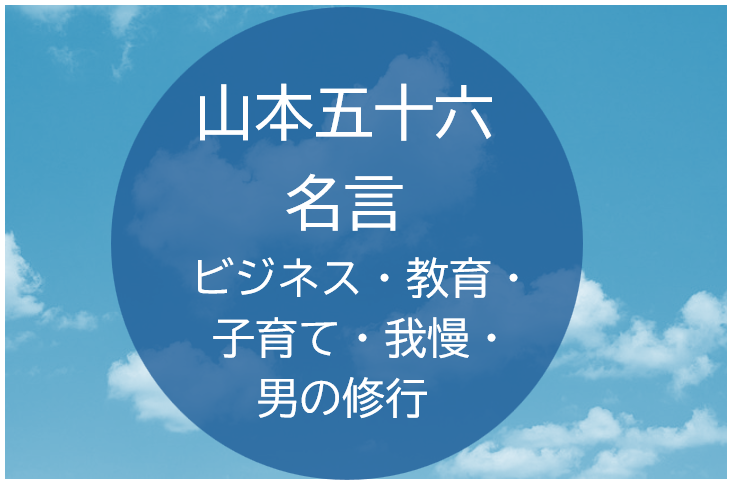

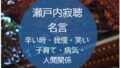
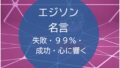
コメント