松下幸之助の、人を育てる・経営理念・感謝に関する名言を紹介します!
彼は「経営の神様」とも呼ばれ、日本を代表する優秀な経営者も中でも群を抜いて高い評価を得ています。
たった一代でパナソニックを築き上げ、1956年には「5年間で売り上げを4倍にする」という計画を立て、わずか4年で成し遂げました。
また、松下幸之助は人材を育てることを大切にし、人を育てることに関する名言を多く残しました。
仕事に対しても、強い確かな信念を持ち、時代に合わせて道を切り開いてきました。
そんな松下氏から紡ぎ出される名言には、どのような意図が隠されているのか見ていきましょう。
この記事を書いた人

人生に影響のある言葉を研究する主婦です。
家にある本は漫画を含めて1000冊を超え、「人生は思考から」をモットーに、歴史上の人物や漫画、スポーツ選手の言葉など様々なところから生まれる名言・格言を紹介します。
松下幸之助の人を育てる名言

失敗したところでやめてしまうから失敗になる。成功するためには成功するまで続けることである。
この名言は、夢や目標を持って行動するならば、諦めずに粘り強く努力を続けることの重要性を表した名言です。
例えば、松下氏が開発した電球ソケットは、最初は全然売れませんでした。
しかし、彼は問題点を分析し、研究と改良を重ねて品質を高め、扇風機の部品として大量受注することに成功しました。
失敗があっても、トライ&エラーを繰り返すことで、それは学びになり、自身を成長させることになります。
もし失敗を理由にして挑戦をやめてしまうと、それが最後の結果になってしまいます。
失敗も成功の一部だと考え、努力を続けることが大切ですね!
人の長所が多く目につく人は幸せである。
人の長所が多く目につくということは、その人の能力や性格、行動において、良いところや優れている点、強みが分かるということです。
人の長所が目につく人は、物事を見るときも、どうやったら「制約」を超えて「可能性」を引き出し、成功や目標達成までたどり着けるかといった、プラス思考の考え方をする人が多いと思います。
そういった見方をすることで、人生で幸せだと感じる機会がより多くなり、豊かな人生を歩むことになるでしょう。
筆者も、人の「長所」や物事の「可能性」の部分を見るよう意識しようと思いました。
人は、他人の悪い部分や気になる点が見えると、それが全体であるかのように錯覚してしまうことがよくあります。
しかし、それは自分にはない価値観や見方であるに過ぎず、多様な見方や価値観を知るきっかけになりますね。
誠実に謙虚に、そして熱心にやることである。
この名言は、目標に向かって取り組む際の大切な心構えを表した名言です。
誠実とは、心がこもっていて偽りがないことです。
謙虚とは、自分自身の能力や地位などにおごることがなく、相手の意見を素直に受け入れることができることを意味します。
熱心とは、物事に対して情熱をこめて一生懸命取り組むことです。
部下に伝えるだけでなく、自らの生き方をもってこの心構えを示した松下氏。
会社が大きくなるとともに、自らの器も大きくなっていったからこそ、この名言が生まれたのかもしれませんね。
以前、どこかの会社の社長が、知恵ある者は知恵を出せ、知恵無き者は汗を出せ、それも出来ない者は去れ、と社員に言っていたことがある。私は部下に大いに働いてもらうコツの一つは、部下が働こうとするのを、じゃましないようにするということだと思います。
「知恵ある者は知恵を出せ、知恵無き者は汗を出せ、それも出来ない者は去れ」と言った社長に対して、松下氏は「これはあかん。この会社は潰れる」と思ったそうです。
案の定、そこの会社は数年後に潰れてしまったようです。
松下氏は自分なら、「まず汗を出せ、汗のなかから知恵を出せ、それが出来ない者は去れ」と言うそうです。
まず汗を出せ、知恵があっても、まず汗を出しなさいと。
「ほんとうの知恵はその汗のなかから生まれてくるものだ」ということが大切だと言っています。
その社員の頑張りや努力をじゃませずに見守る、親のような姿勢でいることが、部下が力を発揮できるカギだということをこの名言は言っています。
人より一時間余計に働くことは尊い。努力である。勤勉である。だが、いままでよりも一時間少なく働いて、いままで以上の成果を挙げることもまた尊い。そこに人間の働き方の進歩があるのではないだろうか。
松下幸之助は、残って仕事をすることも尊い努力で意味があるが、効率的に働くことも大切だと考え、社員に対して無駄な時間や手間を省くよう指導しました。
実は、週休2日制を初めて導入したのも彼なんです。
休みを2日にしたのには大きな意味があります。
1日は休養のため、もう1日は教養のためだそうです。
より短い時間で、高い質を保ち、成果を上げようとすることで、知恵や工夫、創造性を発揮することができますね。
一切のものには寿命があると知ったうえで、寿命に達するその瞬間までは、お互いがそこに全精神を打ち込んでゆく。そういう姿から、大きな安心感というか、おおらかな人生が開けるのではないかと思う。
命には限りがあるからこそ、自らの使命を悟り、そこに向かって全身全霊をかけて取り組もうとする強い意志が伝わってきます。
いただいた命や、人に対する深い敬意が溢れていますね。
よく人の意見を聞く、これは経営者の第一条件です。私は学問のある他人が全部、私より良く見え、どんな話でも素直に耳を傾け、自分自身に吸収しようと努めました。
この名言は、人の話や意見を素直によく聞くことで、自分にはない知識や考え方、価値観を知り、吸収できることを示唆しています。
自分にない部分を、他人から学ぼう、吸収しようという思いがあるからこそ、相手に重心を寄せて聞くことができるのではないかと感じます。
人生における成功の姿は、予知できない障害を乗り越え、自分に与えられた道を着実に歩んでいくことにあらわれる。
人生には困難がつきものであり、勉強や仕事、恋愛、人間関係など、自分の限界を感じるとき、人にとってぶつかる障壁は様々ですが、誰でもそれに苦しむものです。
人生における障壁は、自分が成長する上では欠かせない存在であり、その壁を乗り越えてこそ初めて人は成長し、次の段階へとステップアップすることができます。
その時の自身の年齢や時代によって、立ちはだかる壁は違います。
しかし、与えられた人生における課題だと思って、真摯に着実に向き合うことで、ひらける世界がありますし、そこに向かう姿こそが成功なのだとこの名言は教えてくれています。
すべての人を自分より偉いと思って仕事をすれば、必ずうまくいくし、とてつもなく大きな仕事ができるものだ。
自分以外の全ての人に敬意を払うことで、自分にはない見方や考え方、価値観について学ぶことができ、仕事のパフォーマンスが上がることを表した名言です。
心配や憂いは新しいものを考え出すひとつの転機。正々堂々とこれに取り組めば新たな道が開けてくれる。
心配や憂いは、できることなら感じたくないと思う人も多いかもしれません。
そういったマイナスの感情は、一日中私たちの心の中に付きまとい、自らの心のエネルギーを吸い取ってしまうからです。
しかし、松下氏は、心配や憂いは避けるべき感情ではなく、むしろ、私たちにとってより良い新しいものを考え出すきっかけとなると言っています。
何が心配や憂いの原因なのかを突き止め、そこに対して正々堂々と取り組むことで、新しい道が開けるのです。
心の持ち方で結果が変わる。楽観か悲観か、積極か消極か。心のあり方如何で、物の見方が変わってくる。
悲観主義は気分によるものであり、楽観主義は意思によるものである、という言葉があります。
自身の気分で悲観的に感じることであっても、思いや考え方を改めることで、楽観的に捉えられるということです。
積極も消極も、自らの意志でどうにでも変えられることなのです。
この名言は、心の持ち方で、ものの捉え方や見方が変わり、現実を変えることにもつながることを示唆しています。
土俵の何百倍かの努力を、毎日たゆまずやってはじめて、1分の土俵で勝負を決する際に効果が表れる。
この言葉は、結果や効果を出すためには、ものすごく多くの努力が必要であることを表した名言です。
努力しているのに、なかなか思ったような結果が出なかった経験はありませんか?
しかし、そこで諦めて努力を止めてしまっては、志半ばの成就で終わってしまいます。
松下幸之助の経営理念に関する名言

経営というものは、天地自然の理にしたがい、世間大衆の声を聞き、社内の衆知を集めて、なすべきことを行っていけば、必ず成功するものである。
この名言は経営において非常に重要な観点を表しています。
まず、天理自然の理とは「循環」を意味します。
自然は与え続けることの循環で成り立っているといわれており、自らが与え続けることでその何倍もの恩恵を受ける事になります。
何一つとして無駄なものがなく、すべてに意味があり、私たちの意図を超えた、計り知れない必然があります。
次に、世間大衆の声についてです。
「大衆」という言葉は、多くの人々を指します。
大衆は、社会全体や大きなコミュニティを象徴する言葉として位置づけられており、多様な人々やその関心事を包み込むものです。
大衆の間では、常に様々な文化や価値観が生まれ、流動的であり、その特徴を知ることで、流行や必要とされるものなどの郷港を理解することに役立ちます。
物をつくる前にまず人をつくる。
松下幸之助は、人材育成の重要性を訴えてきました。
こんなエピソードがあります。
当時、創業したばかりの松下電気器具製作所は、まだまだ小さく名も知られていない町工場で採用面接に来るのは、他の会社が採用しないような人たちでした。
さらに、採用したとしても出社してくれないこともあったのです。
そのような中で、ある子を雇った翌日に松下氏は外で、その子が来てくれるかどうかを待っていたそうです。
そして、その子の姿が確認できると急いで中に入り、何事もなかったかのようにその子を迎えました。
このように、松下幸之助は、「社員は大事にしなければならない。大事に育てれば必ず育つ」という信念を大切にしていました。
「企業は人なり」という企業の在り方の本質に関わる名言も残している松下氏。
それだけ、人材育成を大事にされていたのですね。
現パナソニックに社名が変わっても、時代や人が変わっても、決して変わることなく受け継がれていく精神でしょう。
十のサービスを受けたら十一を返す。その余分の一のプラスがなければ、社会は繁栄していかない。
giveの精神の大切さと、社会は与えることによって成り立ち、繫栄していくことを表した名言です。
松下氏は、しばしば経営には、天理自然の理を理解することが大切だとも言っています。
それは、自然は、お互いが与え続けることの循環によって成り立っているからです。
与え続けると同時に、自らも多くの限りない恩恵を受けている感謝を忘れないことが大切ですね。
松下幸之助の感謝に関する名言

感謝の心は幸福の安全弁
感謝と幸福感は相関していることを表した名言です。
様々な場面で感謝できるようになると、総じて幸福度も上がっていくということです。
決して失敗を運やツキ、他人のせいにしてはならない。そして成功は自分の力量とうぬぼれないこと。
この名言は、成功と失敗とでは、持つべき考え方が全く反対であることを教えてくれています。
失敗を運やツキ、他人のせいにしてしまうと、自分に足りなかった部分を改善するきっかけを逃してしまうことになります。
失敗から学びを得るには、自分の力量不足だった部分を見つめ直し、次はどうすれば失敗しないかを考える必要があります。
一方で、成功した場合は、自分の力だと思うことは反対にうぬぼれや傲りといった、ごう慢な感情を引き出してしまい、次なるステップへ進むことを阻んでしまいます。
しかし、周囲のおかげや助力があったからこそ成功できたと思うことで、感謝や謙虚さを忘れずにいることができますし、自分も誰かの力になれるよう、頑張ろうというエネルギーが湧いてきて、次なるステージへ向かうことができます。
経営者にとって大事なことは、何と言っても人柄やな。結局これに尽きるといってもかまわんほどや。
経営者として成功するために最も大事な要素は人柄であることを伝える名言です。
では、どのような人柄であればよいのでしょう。
ます1つめはgiveの精神です。
成功する人の特徴の一つとして、見返りを求めず、与え続ける精神を常日頃から持っていることが挙げられます。
2つ目は感謝することです。
成功する人は、どんなに小さなことでも、どんな状況に置かれていても感謝の心を忘れません。
松下氏は、同じ職場で働く人に対する、暖かい心や思いやりの心を大切にしてきました。
3つ目は誠実で素直な心です。
誠実とは、物事をまじめに一生懸命に考え、それに取り組む姿です。
素直な心とは、自分の至らなさを認め、そこから努力する謙虚な姿勢のことです。
素直な心であれば、何が正しくて何が正しくないか自ずとわかると、松下氏は言っています。
同じく経営者の渋沢栄一も、心の大切さを説いた名言をいくつも残しています。
渋沢栄一の名言記事はこちらです。
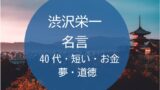
渋沢栄一の名言~40代、50代はハナ垂れ小僧・短い・お金・論語と算盤・夢七訓・道徳~
「日本近代経済の父」と呼ばれ、第一国立銀行を設立し、その他数多くの企業の設立に携わった渋沢栄一は、明治から昭和にかけて活躍した実業家です。 設立に携わった企業の数はなんと500以上にも及びます。 2024年発行の新一万円札の顔にもなりました...
誠意や真心から出たことばや行動は、それ自体が尊く、相手の心を打つものです。
言葉や行動にはエネルギーがあり、その人の人柄が垣間見えます。
誠意や真心のこもった、心からのことばや行動というのは、相手の心にも響くものがありますね。
恵まれた生活も結構だし、恵まれない暮らしも結構、何事も結構という気持が大切だと思います。
この名言は、どのような境遇にあっても、与えられた環境や暮らしに感謝し、前向きに物事を考えることの大切さを言っています。
「恵まれた」「恵まれない」というのは主観であり、自身の考え方次第で変えることができます。
他人を羨んでも何も変わりません。
恵まれていることの基準は、決して物が豊かなことやお金持ちなことだけではないはずです。
今の状況に感謝することで、人生を楽しむことができるのではないでしょうか。
優越感や劣等感を捨て、自分が今生きていることを存分に味わうことを呼びかけられている気がしますね。











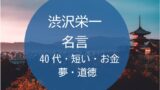


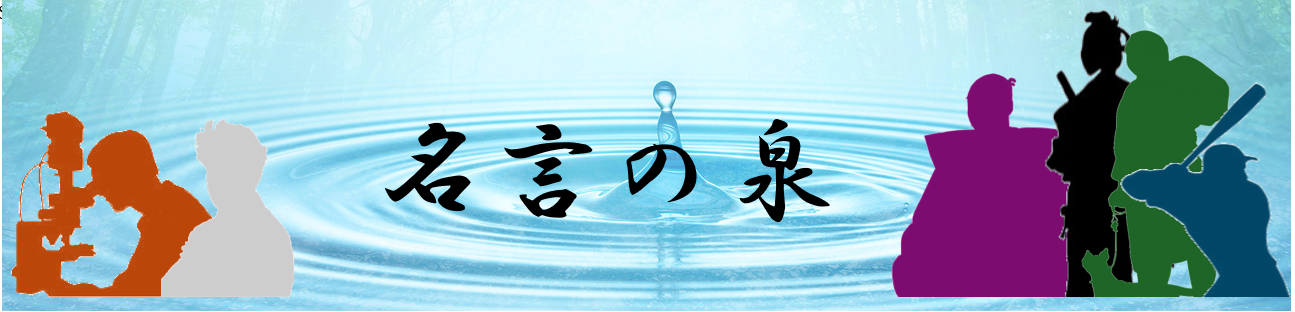
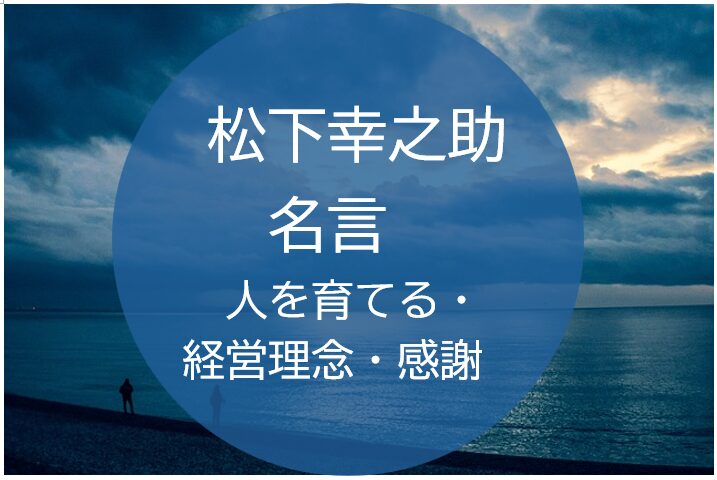

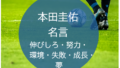
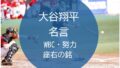
コメント