明治時代の啓蒙思想家であり、慶應義塾大学の創設者でもある福沢諭吉。
1万円札の顔の一人としても、多くの人に知られています。
そんな彼は、明治維新の激動の時代を生き、日本の発展に寄与した偉大な人物でもあります。
福沢諭吉は、「天は人の上に~」で始まる大ベストセラー『学問のすゝめ』を著し、人生において大切にしたい心訓や名言を多く残しました。
それらの名言にはどのような意味があるのか見ていきましょう!
福沢諭吉の名言~人の上に~

これは、福沢諭吉の名著『学問のすゝめ』の冒頭部分で、聞いたことがある人は多いのではないでしょうか。
全ての人は平等であり、社会的地位や生まれによる差別はないといった意味があります。
当時は、明治維新が起き、廃藩置県によって武士は皆失業状態でした。
士農工商の身分制度が終わりをつげ、四民平等が始まりました。
一見、階級社会がなくなって良かったと思われがちですが、全員が同じスタートラインに立ち、自分の人生を自らが築き上げなくてはならなくなりました。
人生のレールを自らがひかなくてはならない中で、福沢諭吉が学問の大切さを説いたことは非常に大きいです。
福沢諭吉は、学問によって国民一人一人を強くし、西洋の国々に負けないような日本国家をつくろうと考えました。
この『学問のすゝめ』は、明治維新の動乱を経て、これから開かれていくであろう新時代への希望と、国家の独立と発展を担う責任を自覚する明治の人々の気概に満ち溢れ、当時の日本国民に広く受け入れられました。
最終的には300万部以上を売り上げ、当時の全国民の10人に1人が読んだとされます。
その後も時代をこえてロングセラーとなり、現在でも多くの人に読まれる名著となっています。
吹沢諭吉の名言~心訓~
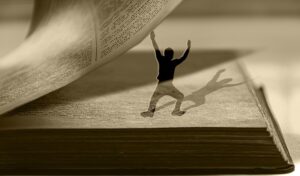
-
一、世の中で一番楽しく立派な事は、一生涯を貫く仕事を持つという事です。
一、世の中で一番みじめな事は、人間として教養のない事です。
一、世の中で一番さびしい事は、する仕事のない事です。
一、世の中で一番みにくい事は、他人の生活をうらやむ事です。
一、世の中で一番尊い事は、人の為に奉仕して決して恩にきせない事です。
一、世の中で一番美しい事は、全ての物に愛情を持つ事です。
一、世の中で一番悲しい事は、うそをつく事です。

しかし、この心訓から、日々の私たちの心の持ち方や行いにおいて学ぶべきことはたくさんありそうですね!
人生で大切にしたい福沢諭吉の名言

この名言は、相手の側に立ってその人を理解しようとすることの大切さを伝えています。
自分の考えというのは、今まで自分が生きてきた環境の中で身につけてきた価値観や視点に過ぎません。
知己(ちき)とは、自分のことをよく理解してくれる友人や知り合いのことです。
そのような人が自分の周りに多いことは、人間の一時的な喜びや満足感につながるとこの名言は言っています。
この名言の通り、自分の力を発揮できる環境に身を置くことで、自分の運命がより良い方向に開けます。
能力があってもそれを思うように発揮できる環境でなければ、自分自身を最大限に輝かせることは難しくなってしまいます。
自分が本当にやりたいことは何かを考え、行動することで現実が変わるかもしれません。
これは、『学問のすゝめ』で述べられた名言です。
人は前進するか後退するかの2択しかなく、物事は常に動いており、停滞することはないという哲学を伝えています。
「進まざる者」とは行動しない者のことで、そういった人は必ず退く運命にあります。
しかし、「退かざる者」つまり諦めずに、逆境や試練の中でも乗り越えようとする者は必ず前に進むことができます。
たとえ失敗や挫折の現実に見えても、精神の面では飛躍的に成長している場合が多いです。
そんな経験を味わった人だけが、つぎなるステージへと進むことができるのでしょう。
あなたがもし何か、積極的な行動を起こしているならば、時には周囲の期待や評価、批判を受けることもあるかもしれません。
しかし、他人からの目や評価に臆せず、気にすることなく、自分の目標や願いに向かって生きる意志が大切ですね。
やってもいないのに、これはできなさそうだと思った経験はありませんか。
やってみることで学べる事、得られるものは多くあります。
自分の先入観を捨て、物事に向き合うことの大切さをこの名言は伝えています。
この名言は、どれだけ学問を修めて知識や情報を知っていても、活用できていないのならば、それは何も学んでいないのと同じことだということを伝えています。
実践に活かせて初めて、その学問というのは生きてくるのですね。
この名言は、努力の大切さを伝えると共に、自分を信じて愚直に努力を続けることで、達成が難しい事柄でも成し遂げることができることを示唆しています。
どうしても達成したい目標や、大きな夢に向かって頑張るならば、試練や挫折を時には経験することもあるかもしれません。
しかし、「継続」は何より大切な事であり、小さなことの積み重ねが、自分さえも想像していないような大きな成果につながることをこの名言は伝えています。
完璧すぎない方が、逆に人間味がありますよね。
結婚というのは、その後の人生をその方とともに歩んでいくのですから、人生において一大イベントです。
本当にこの人と一緒になってよいのか、慎重に考える必要があることをこの名言は表しています。
とはいえ、頭で考えすぎても、答えが出るものではありませんし、正解があるわけでもありません。
こういった答えのない大切な問いこそ、直感やインスピレーション、フィーリングが活きてくるのではないかと思います。

筆者は、夫と付き合っている頃に、今でも覚えている出来事があります。
当時の筆者は体調があまりよくなく、精神的にも不安定でした。でも、夫はそんな私を前にしても動じる様子は全くなくいたって自然体でした。
良いのか悪いのか、そんなに気を遣っていなかったのかもしれませんが(笑)
ある日、まだ付き合って浅いとき、2人で食事をしていると、身体に電気が走ったかのようになり、なぜか「この人と結婚する」と、自分の思いのようでそうではない言葉が湧いてきました。
結婚までには、色々とまあありましたが、今の幸せがあるのは、夫と結婚できたからだと、直接本人に言うのは照れくさいのでこの場を借りて言っておきます(笑)
これは、勝敗という結果だけを見てその人物を評するのではなく、その人の思いや結果に至るまでの過程を見ることの大切さを伝えています。
「貴賎なし」というのは、貴いものと卑しいものの区別がないという意味です。
人は生まれながらにして、貧乏だったりお金持ちだったり、その後の人生の身分の差が決まっているわけではありません。
ただ、学問に励み、努力をした者は貴人となり富を得る可能性が高くなり、学問のない者はただ使われるだけの貧乏人になってしまうことを伝えています。

まさにその通りだと思います。筆者は専門学校卒の母と、地方国公立卒の父のもとに生まれました。
父から勉強に関して何か言われた記憶は全くなく、どちらかというと母のほうが教育ママでした。
そんな母親の方針に対して反発する思いを持った時期もありましたが、今の私があるのは、自ら学ぶことの大切さを重んじて育ててくれた両親のおかげだと思っています。
あくまでこれは、学問は大切だという考えの一つに過ぎず、そうでない考えもあると思います!

筆者のママ友のお家で、そのママ友も旦那さんも高校卒業後、就職しているお家があります。
そのママ友は、自分の子を、就職率が高い家から通える高校に進学させたいと話していました。
大学に進学したことで世界が広がった経験をした筆者からすると、もったいないと思うのですが、自分の価値観だけで相手を評するべからずと、とどまり(笑)
そんな考えの人もいるよねと思った出来事でした。
自分の悪かった点を認めるというのは勇気がいりますが、とても大切で立派なことです。
自分の至らなかった点に気付けること、それをすぐに改善できる柔軟性は、多くの人と関わり合いながら生きる私たちにとって重要なことです。

筆者は先日仕事で、同僚との思いのすれ違いにより、仕事が進まなかったという出来事がありました。
自分の至らなかった点や、相手の状況を考え切れていなかったことをすぐに謝罪し、自分の思いを通そうとしたことを謝りました。
数日間は「やってしまったなあ」といった思いに苛まれましたが、時間薬が解決してくれた部分も大きいです。
人間は誰でもミスをします。
気が付いた時点で改めることの大切さを学んだ経験でした。
これは、自ら働いたお金で、自分を食わせ、養い、生活していくことが自立した人生の基本であることを伝える名言です。

筆者は、現在の教育関連の仕事は自分にとってかなり激務でもう辞めたいと思うこともしばしばあります。
しかし、働くことが、自分の存在意義や自尊心につながっている部分もあり、ただお金を稼ぐためだけではない大切な意義があると感じております。
この名言は、「農業をやるなら大農家を、商業をやるなら大商人を目指しなさい」という意味の言葉で、「学問のすゝめ」に出てきます。
明治時代には、自分の得意なことを極めて日本の第一人者を目指そうとした若者が多くいました。
志を高く持ち、本気で叶えようと努力をすること、やるからにはどんなことも挑戦し、やってみることは大切なことですね。
これは、勉強をするのは、どんな環境でもできることを伝える名言です。

筆者もよく、時間がかかりそうな数学の問題や物理などの問題を覚え、入浴中や食事中に考えていました。
その方が、じっくり考えることができ、自分にとって有益な勉強方法でした。
空想は、言い換えれば、ヴィジョンや青写真の元となります。
人類の文明や技術の発展は、「こうなったらいいな」「こうしたいな」といったいわば頭の中に描かれた空想、青写真から、具現化されていきました。
人間の中にある、一人一人の可能性の無限さには、私たちの人知を超えたものがあると感じます。
一見して「無理だ」「できない」と思われる事柄でも、信じて向かうかは自分次第です。
空想も、具現化されればそれは現実となるのです。
福沢諭吉は、明るく肯定的で、精神力のある性格でした。
たとえ軽蔑や侮辱され、心無い言葉を言われたとしても、自他を責めることなく、簡単にはマイナスの感情を他人にぶつけるといったことは決してしない性分だったのでしょう。

筆者は、心無い言葉を聞くと、すぐに落ち込んだり、怒りや悲しみの気持ちで一杯になってしまいます。
自他の感情や言葉に振り回されない強い精神力をつけることが必要だと、この名言を聞いて感じました!
この名言は、「思考・言論・著述」は「直接的な暴力」よりも人々にとって影響があると言っています。
文章で表現される思想は、多くの人に読んでもらえ、早い速度で人々に広まり影響を与えます。
さいごに
いかがでしたでしょうか。
福沢諭吉の名言には、時代を超えて、人間性を磨くための重要なヒントがつまっていました。
当サイトでは、他にも偉人の名言を紹介しています。
同じく一万円札の肖像となった渋沢栄一の名言記事はこちらです。
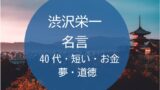
最後まで読んでいただきありがとうございます。
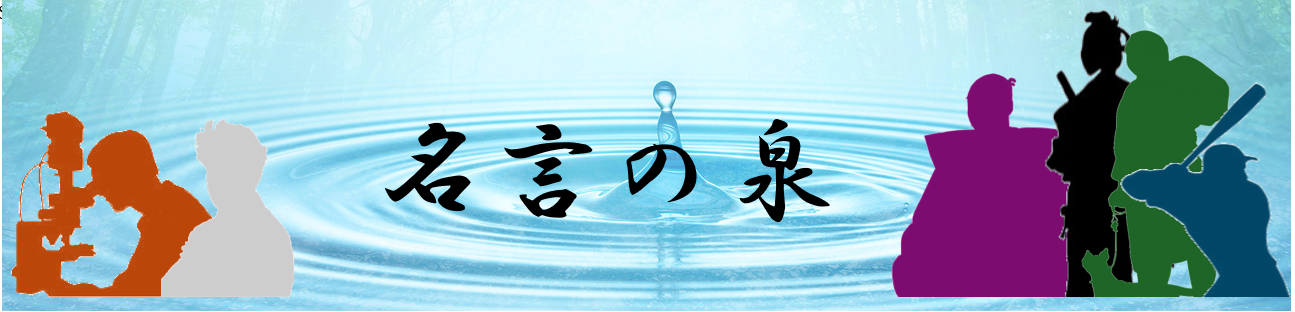




コメント